子育てはお母さんのあり方が9割!
こんにちは!
ママの心の傷を癒して、
幸せな子育てに導く専門家、
元教師で
現在子育てカウンセラーの
沙咲 晴美(たれぱんだ)
です。

10時~18時(時間外相談可能) zoomを使用します【全国対応】

子育てはお母さんのあり方が9割!
こんにちは!
ママの心の傷を癒して、
幸せな子育てに導く専門家、
元教師で
現在子育てカウンセラーの
沙咲 晴美(たれぱんだ)
です。

躾と過干渉の線引きって、
むずかしくないですか?
「子供のことをきちんとしつけなきゃ!!」
と思って、
まじめにきちんと子育てをしているはずが、
「実は過干渉だった・・・」
ということがあったら、
ちょっとショックですよね。
でも、考えてみれば私たちって
子育てについて
あらかじめ学んでいないわけですよね。
過干渉の弊害は、
時間が経ってから出てきます。
なので、
自分のやっていることが
ちゃんとした躾なのか、
それとも過干渉なのか、
知りたいお母さんや、
「しつけと過干渉はどう違うの?」
と疑問に思っているお母さんのために、
私の実例をもとに
説明してみようと思います。
知っているだけで気づきにつながり、
・無気力でやる気がない
・いつまでも親に依存する
・自己肯定感が低い
・自分で考えられない
→問題解決力がない
・自立できない
などの
過干渉の弊害を
防ぐことができます。
少しでも参考になれば、
嬉しく思います。

私が長女に関して
気になっていたことは
いくつもありましたが、
その中の一つに
「片付けをしない」
ということがありました。
長女はものすごい
「めんどくさがり屋」さん。
「使ったものをすぐに片付ける」
とか、
「小学校の時なら
(給食の時使う)お箸を、
中学以降は
お弁当箱を帰ってすぐに出す」
というようなことが、
高校を卒業するまで
ついに定着しませんでした。

しないのか、できないのか・・・
あるいは、
私がうるさすぎたのか・・・
自分の部屋に持って行った
飲み物を入れたコップやグラスも、
いつまでも放置されたまま・・
ということも ザラでした。
当時の私は、そんな時
どうしていたかというと・・・・
見つけた時に本人がいる場合は、
とにかくガミガミ言い
(我慢できない!)
すぐに洗うか、
せめて流しまで持っていくように指図し、
持って行くまでうるさく言い続け、
それでも持って行かない場合も
多々あったので、
最後は雷を落とし、
無理やりさせていました。

また、
見つけた時に本人がいない場合は、
私が撤収していました。
(もちろん、後で説教です。)
小さい頃は、言われるままに
行動していた長女も、
思春期にさしかかる頃からは、
激しく反抗するようになりました。
私は、
その可愛げのない言動に腹を立て、
売り言葉に買い言葉がエスカレートし、
毎回ひどいケンカになっていました。
そして、
肝心の「コップをかたづける」
という行動は
いつまでたっても身につかず、
長女の私に対する反発心ばかりが
大きくなり、
いつまでたっても
「いたちごっこ」でした。
ああ、本当にしんどかった~~!!

さて、
この私の行動は
しつけでしょうか、
過干渉でしょうか?
なぜ、
私がその場ですぐに
コップを持って行かせたり、
本人がいない場合は
私が持って行ったりしていたのか?
もちろん
「すぐに洗う、
もしくは流しまでもっていく
という行動を身につけてほしい」
という気持ちはありましたが、
それ以上に、
使ったコップをいつまでも
置きっぱなしにしているのを見るのが
ものすご~~~く嫌!!
だったからです。
何故嫌だったのか?
それは
「だらしないことはダメなこと」
と、強く強く信じていたから。
そして、
娘がだらしないのは
自分の子育てが
間違っているのではないか、
私がダメな母だからではないのか?
そんな 不安 や 恐怖 があったのです。

つまり、
「自分はダメではない」
という証明をするために、
「自分はダメな母親かも」
という不安や恐怖から逃れるために、
長女の行動を
何が何でも変えさせたかったんだと思います。
長女がいない時は
すぐに私が撤収していたのも、
同じ理由からです。
こういう
「不安」や「恐怖」「嫌悪感」などの
感情的に支配された行動は、
しつけではありません。
感情に支配されると
何が何でも自分の思い通りに
子供を動かそうとしたり、
その結果口うるさく指図したり、
子供の代わりに
親がやってしまったりするのですが、
これが、過干渉の特徴です。
当時の私もそうでしたが、
過干渉になってしまう親は
不安や恐怖の感情に
支配されていることが多いのです。
しかし、
親が手出し口出ししすぎることで、
子供は
「コップを放置していたらどうなるか」
という 自然の結末 を
体験することができなくなります。
その後、アドラー心理学で
『課題の分離』を学び、
過干渉の弊害を知ってからは
極力手出し口出しをしないように
努めました。
(ある意味、自分との闘いでした。)

朝、家族を送り出した後、
家中の窓を開けて換気をするために
子供の部屋にも入りますが、
その時コップやペットボトルが
置きっぱなしでも、
絶対に私が持っていくことは
しないようにしました。
(かなりの忍耐が必要でしたが)
そして、時々
「使ったコップやペットボトルは
ちゃんと洗うか、
せめて流しまで持ってきてね。」
「ほったらかしにしておくと、
カビが生えるよ。」
と伝えるようにしました。
ただ伝えるだけ。
すぐに持ってくることを
強制はせず、
余程のことがない限り
本人に任せていました。
ある時
ついに置きっぱなしのコップに
カビが生えました!
それを見た長女は
びっくり仰天![]()
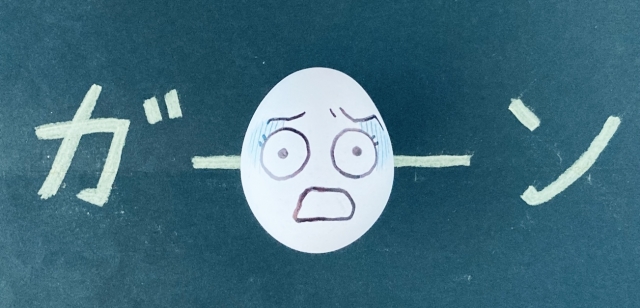
その時初めて
使った後のコップを
長期間放置するとどうなるのか、
カビが生えると
どれほど気持ちが悪く
グロテスクになるのか、
ということを目の当たりにしたのです。
(中学生だったか高校生になっていたのか
忘れましたが、その歳まで
カビが生えるとどうなるかを
知らなかったのは、
ひとえに
私の過干渉な子育ての産物ですね。)
キャーキャー言いながら、
慌てふためいて
私に知らせに来ました。
私は、
「どんなに気持ちが悪くても、
自分がしたことだから
自分で洗わないとね。」
と言いました。
長女もそれは納得したようで
大騒ぎしながらも
自分で洗いました。
それ以降、長女は、
使ったその日に・・
とまではいきませんが、
そんなにひどい状況になる前に
自分の使ったコップやお皿を流しまで
持ってくるようになりました。

過干渉の問題は、
子供に失敗体験をさせまいとして
「転ばぬ先の杖」を
与えてしまうこと。
その結果、
例えばこのケースなら
「使ったコップを
長期間放置するとどうなるか」
という自然の結末を
体験できないのです。
でも、今回のように
自然の結末を体験することによって、
一発で長女は「学んだ」のです。

しつけとは、
必要なことは子供に教える
(伝える)。
しかし、子供がどうするかは
一旦子供にまかせ、
自然の結末を体験させる。
そしてその結果
起こったことの責任は
自分でとらせる。
ということなのです。
「自然の結末(しばしば失敗)を
あえて体験させて、
自分のしたことの結果を見せて、
責任をとらせること」
これが躾ですね。
この時大切なのは、
感情的に怒らないこと。
決して子供を責めないこと。
なぜなら、
子供の失敗は悪ではなく、
学びなのですから。
そして、
もし自然の結末を体験することで
子供が辛い思いをしたのなら、
その辛い気持ちに
しっかり共感してあげるのが、
親の仕事。

その結果、子供の行動が変わり、
成長するのです。
過干渉ではなく、
正しい躾をしていくと、
子供は
失敗からたくさんのことを学び、
しっかりした芯ができて、
大きく成長していくのです。
あなたの子育てを
応援しています!
今日もお読みいただき
ありがとうございました。
